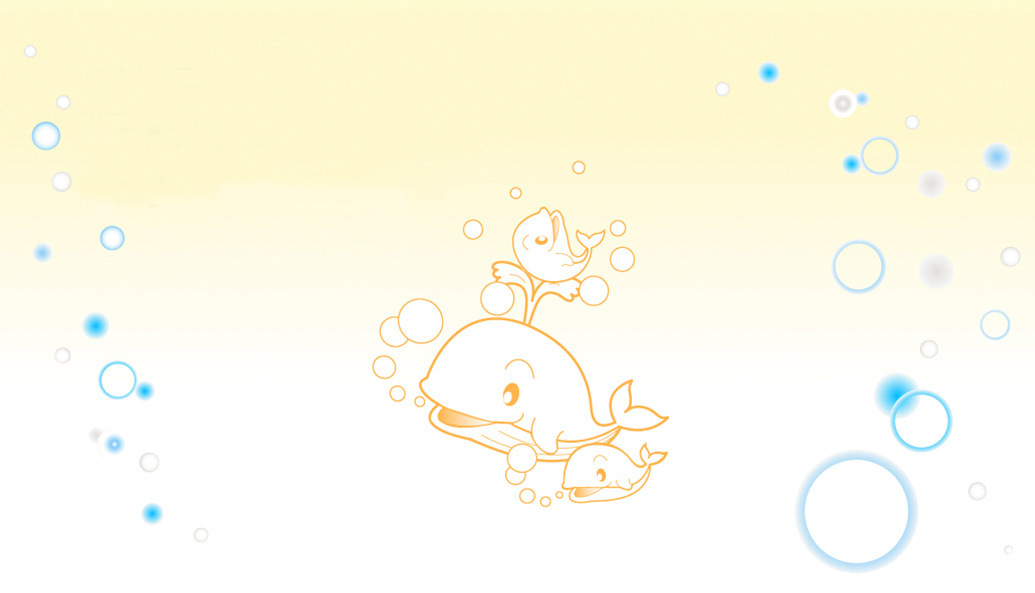良くあるご質問
熱性
けいれん
6歳未満の小児において、38°C以上の発熱にともなって起きるけいれんです。急な発熱の前後に起きるひきつけで、検査をしても髄膜炎や脳炎、代謝異常などの基礎疾患が見られない場合にこの病名がつきます。
ひきつけが起きた時は?
【口の中に指を入れない】
ひきつけている時には、口の中に指や箸入れるなどの余計な行為はしないようにしましょう。舌を咬む事はまずありません。かえって誤飲や嘔吐を誘発することがあり危険です。
【楽な姿勢で】
体を横に寝かせ、衣服を緩める、ピンなどの危ないものは取り外すなどして、呼吸を楽にして、安全な体位にしましょう。
【吐くと危ない】
吐き気があれば体ごと横に寝かせ、吐いたものが喉につまらないように気をつけましょう。
【けいれんの様子を覚えておく】
時計を見てけいれんが何分続いているか、けいれんの様子を診察時に詳しく伝えられるようにしましょう。
【あわてない、あわてない】
ひきつけは通常、数分間(だいたい5分間以内)でとまります。ほとんどの場合、生命を脅かされたり、後の後遺症を残すことはありません。
*症状
・目の向き
・顔色
・呼吸の状態
・手足の動きや左右差
・体温
病院の受診は?
初めての発作時は、どなたも病院に受診されると思いますが、一度熱性けいれんと診断がつきましたら、発作の度に受診する必要はありません。ただし、以下のような時には単純な熱性けいれんではない場合もありますので、病院を受診してください。
*けいれんが10分以上続いてとまる様子がない時。
*1日に2~3回以上けいれんが起こる時。
*いつものけいれんと違う時(けいれんが終わった後も意識が戻らない、呼吸状態が悪い、応答や姿勢がおかしいなど)
ひきつけの予防は?
再発の可能性の高いお子さんには、病院からひきつけ止めの座薬が処方される場合があります。熱性けいれんは熱の上がりはじめから24時間以内がおこりやすいといわれています。発熱にきづいたら、1回目のけいれん止めの座薬(商品名:ダイアップ)を入れ、発熱が続くようでしたらその8時間後にもう一度座薬を使用します。2回使用することによって、けいれんを抑える効果は8時間持続し、熱が続いても発作の起きる可能性は低くなります。熱さましの座薬はダイアップを使用後30分くらいあけて使いましょう。
薬の
飲ませ方
小さいお子さんへの薬の飲ませ方は・・?
・親は、薬を与える事の重要性を充分認識したうえでお子さんに接する事が大事です。
・お話が理解できる年齢のお子さんには、はじめに薬を飲む事の必要性をしっかり説明してあげる事が大切です。
・薬は、指示された量と回数を守りましょう。
・こども用の薬は、基本的に胃を荒らす心配は少なく食後内服薬でも特別な指示がなければ空腹時少量の水分を与えた後に飲ませて構いません。
・胃腸症状(嘔吐)が強い時、咳でむせて吐いてしまう時には工夫が必要です。
*少量の水分でも摂取できればその後に飲ませてみましょう。(食事前でも構いません)
*分割して、少量ずつ飲ませてみましょう。
*内服後30分は飲食を控えましょう。 *どうしても薬が飲めないときは、主治医に相談しましょう。
*どうしても薬が飲めないときは、主治医に相談しましょう。
・授乳期のあかちゃんの場合
*ミルクに薬を混ぜない方が良いでしょう。(ミルクが嫌いになることがあります)
*授乳後、ゲップといっしょに吐いてしまう事があるので排気をしてあげましょう。(背中をやさしくトントンたたき飲み込んだ空気を出します) あかちゃんの胃腸機能が未熟な為逆流したミルクが口からダラダラ出てくる生理現象があります。(いつ乳)このようなことが起きやすいので、お薬を与える時は授乳前後30分位はあけるようにしましょう。
*薬を飲ませた後しばらくは抱っこ等、上体を高くしておくと良いでしょう。
・保育所に通園されていて1日3回の規則的な内服が不可能な時、2回目の内服時間に合わせて3回目の内服時間を遅くする等、時間調整しましょう。(薬の間隔は最低4~5時間以上あけてください)
・親は薬の味を知っておきましょう。苦味の強い薬の場合は、苦味を軽減させる工夫をしましょう。(食品に混ぜる、挟む、のせる・・・)
*相性の良い食品
・マクロライド系抗生物質(クラリス)例:練乳、アイスクリーム、チョコクリーム、プリン
・抗ウイルス剤タフミル例:チョコアイス、いちごヨーグルト、ココア、スポーツ飲料
*全体的に苦みが増す傾向にある食品例:果汁ジュース、スポーツ飲料、乳酸飲料、ヨーグルト
*注意事項
・味覚には個人差があります、親が味見をしてから少量ずつお子さんの反応を見て与えて下さい。
・食品と混ぜた薬は時間の経過で品質が変わる可能性があるため保存する事はできません。小まめに一口ずつ混ぜて与えてください。
・薬が飲めた時は、しっかりとほめてあげてください。
・薬がどうしても飲めない時は、主治医、スタッフに遠慮なくご相談ください。
2.シロップ剤は?
・冷蔵庫で7日~10日位の保存です。
・泡立てないようによく振って中身を均一にしましょう。
・指示された量は計量カップ等で計りましょう。
・乳児にはスプーンやスポイトなどで頬の内側に落として少しずつ飲ませ、口直しに水やぬるま湯を飲ませます。
3.粉薬は?
・直射日光、高温、多湿を避けた状態で半年位の保存です。
・水に溶かす場合は、2~3日で飲みきれる量にしましょう。(2~10cc)
・乳児の場合は少量の水で練り、頬の内側や上顎につけ少しずつ水を飲ませます。
4.ドライシロップは?
・子どもが飲みやすい甘みをつけられた細粒の薬です。そのままで飲ませるか、水に溶かす場合は、2~3口で飲みきれる量で溶かしましょう。
・一緒に処方されたシロップ剤と混ぜても飲みやすいです。
5.カプセル錠剤は?
・噛んだり、カプセルの中身を出したりしないようにしましょう。
・座らせた状態で飲ませましょう。(誤飲して気管に入ることがあります)
・飲んだ後、口の中に残っていないか確認しましょう。
子どもさんの発育や健康相談、予防接種、病気の心配などお気軽にご相談ください。お子さんの病気だけではなく、発育や発達、ちょっとした心配事など、いつでもお気軽にご相談ください。
予約なしでも来院していただけます。